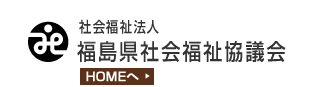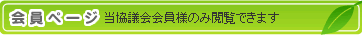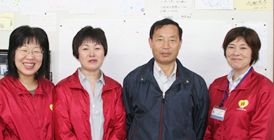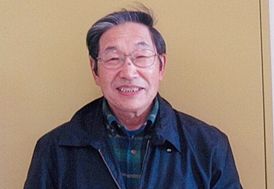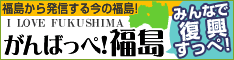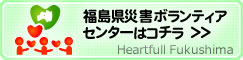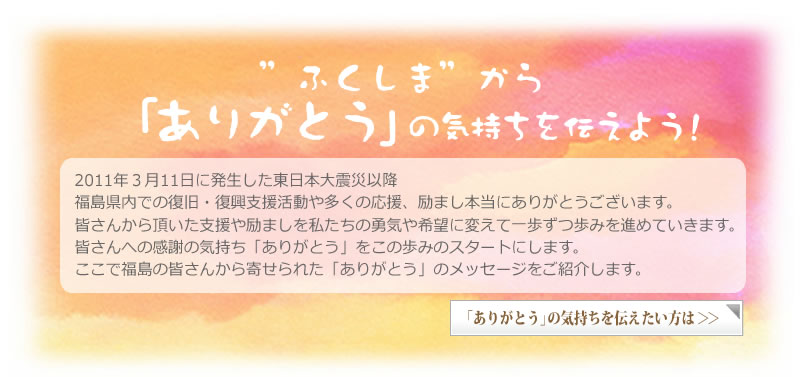
| 「たくさんの“ありがとう”を伝えたい」 | |||
| ■ 塩沢農村広場応急仮設住宅 自治会長 熊川勝(浪江町) | ありがとうの言葉(53) |
||
|
震災後、一番感謝の気持ちを伝えたいのは津波で亡くなった女房です。家内の遺骨は放射能で持ってくることができないため、まだ浪江の部屋にありますが、毎日語りかけています。 被災してから感謝の気持ちが込み上げる場面はたくさんあります。人に親切にされる度、俺は1人じゃないと思えました。 津波で流され裸で櫓の上にいたところを迎えに来てくれた兄貴。娘のところに身を寄せようにも、飛行機も全て止まっていた須賀川の空港ロビーで塩原からタクシーがでるという情報を教えてくれた青年。瓦礫の上を裸足で逃げたため釘が刺さった足の治療を迅速にしてくれた横浜の病院スタッフ。津波でなくした免許証を最優先で再発行してくれた神奈川の免許センターや、携帯電話を無償交換してくれた携帯ショップ。 4月14日、遺体捜査が入った浪江町で妻を探すため、飛んで帰った二本松市では、復興作業員の宿泊で二本松駅周辺のホテルは全て満室…しかし1部屋空けて、途方に暮れていた私を無償で泊めてくれた、ある宿の女将さんと旦那さん。二本松から浪江までの長距離を「代金はいらない」とメーターを0にしてくれたタクシー運転手。暑さのため遺体が臭う中、遺体捜査をしてくれた若い警察官。そして6月、家内の遺体が見つかり、快く供養してくれたお寺の住職…。 人間はこういうときに思いやりをひしひしと感じます。常に感謝。“ありがとう”という言葉を忘れてはいけません。仮設住宅の人々はお互いに“ありがとう”と言い合っているから明るく前を向いていられるのです。 |
||
「生活を支えてくださる皆さんに感謝」 |
|
| ■ 旧平石小学校応急仮設住宅 自治会長 天野淑子(浪江町) | ありがとうの言葉(52) |
2011年11月に今の仮設住宅にやってきました。最初は家にこもってばかりでストレスも強く感じていました。そんなとき叔父に薦められ、新しく立ち上げられた婦人部の部長となりました。それからは婦人部で集まってお話しをしたり、手芸会を開催したりと楽しみができ、気がまぎれてきました。ここの仮設住宅に住む人々は私と同じ浪江町から避難してきましたが、震災前までは知らなかった人ばかりです。なので、今こうして互いに支えあい、活動に参加してくれることに感謝しています。 また、この仮設住宅にはボランティアとして多くの方々がきてくださっています。女性会の方々から野菜をいただいたり、カンベンガ・マリールイズさんを中心に「ルワンダカフェ」を開いていただいたり、東京からの美容師さんにカットをしてもらったりと、わたしたちを元気づけてくださっています。このような方々に色紙や写真ハガキをつくり礼状をだすことで“ありがとう”の気持ちを伝えています。そして震災後の治安を守る「ウルトラ警備隊」の皆さんが夜中に見回りをしてくださって、仮設住宅でも安心して過ごしています。私たちの生活を支えてくださる皆さんにとても感謝しています。 |
|
| 「集会所は仮設住宅のオアシス」 | |||
| ■さきあみクラブ広畑の華(新地町) | ありがとうの言葉(51) |
||
|
「さきあみクラブ広畑の華」は、現在12名で活動しています。仮設住宅の集会所に、週1度メンバーが集まり、布を切る人、裂く人、編む人等に分かれて、コースター等の作品を制作しています。売上は、仮設住宅の集会所でのお茶会やサロン活動などの費用に使わせていただいています。 集会所に遊びに来る子どもたちの見守り役としても、一役買っています。同じ仮設住宅に暮らす子どもたちは、「みんなの子ども」。クラブの活動時間中、遊びに来た子どもたちの様子を静かに見守っています。お母さんたちからは、「見守ってくれるメンバーの方がいるから安心して遊びに行かせられます」との声も聞かれます。 こんな活動ができるのも、端切れ布を届けてくださるボランティアさんたちのおかげです。ありがとうございます。これからも、引き続き集会所が仮設住宅のオアシスになれるよう、活動をがんばります。
|
||
「 被災して初めて分かったボランティアの重要性 」 |
|
| ■ 広畑仮設住宅女性部 代表 吉村恵子(新地町) | ありがとうの言葉(50) |
震災以降、新地町には町の社協さんをはじめとするたくさんのボランティアの方にお世話になりました。食事や支援物資の提供、また温かい心遣いなどでありとあらゆる支援をしていただき、ありがたいことばかりです。 私は、もともとボランティア活動が大好きで、震災前は新地町ボランティア連絡協議会の会長も務めておりました。しかし、いざ自分が支援される立場になって、改めてボランティアのありがたさに気付くことになりました。これは、被災してみないとわからなかったことだと思います。 今では、仮設住宅の住民の皆さんがお互い元気に協力し合って、前向きに毎日を過ごせるよう頑張っております。今でも、毎月のお茶会や集まりなどでボランティアさんの協力が欠かせません。過去は過去として大事にしながらも、前を向いていきたいと思います。 ボランティアの講師を迎え、集会所で「はつらつ健康体操」の運動をしています。
|
|
「子どもたちの笑顔に感謝」 |
|
| ■ 渡部 昭子(相馬市) | ありがとうの言葉(48) |
3・11の震災以来、“ありがとう”の言葉の尽きる日はありませんでした。道路を行き交う支援の自動車にはもちろん、そのトラックが走れる状態を一生懸命保ってくれた道路にも感謝の気持ちで頭が下がりました。 あれから2年。公園で遊ぶ子どもたちの姿はあまり見かけませんが、子育て支援チビッコ広場は子どもたちの歓声でいっぱいです。何事もなかったかのように元気に走り回っています。その姿に励まされているのは大人たちです。特にスマイルパークの屋内遊具施設が開設された時の喜びは、まさに天使のような輝きでした。うれしさを全身で表現して遊ぶ子どもたちの姿に癒され元気をいただいたのは大人たちです。 子どもたちの笑顔は素敵で、希望の光でもあり、元気の源でもあり、癒しでもあり、子どもたちに会う喜びに感謝!感謝!の日々です。
|
|
| 「 利用者の皆さんに、そして仲間へ 」 | |||
| ■
ハッピー愛ランドデイサービスセンター
看護師 茨木 尚美(写真右側) ・ 介護員 馬場美枝子(写真左側) |
ありがとうの言葉(47) |
||
|
震災があった日も、デイサービスをしておりましたので、自宅に帰れなくなった方や独り暮らしの方にそのまま宿泊してもらい、数日過ごしました。水も電気もない中、公休の職員も家族と共に駆けつけ、職種も職員も関係なく一丸となって団結し、家族の方までもが施設内の片づけ等を手伝っていただきました。 震災直後には電話がつながらなかったので、デイサービス利用者宅をすべて訪問することにしましたが、信号や道路事情が悪く、思うように訪問できずに夜までかかって2日で100件以上を職員で手分けして訪問しました。やっと直接お会いできた時は、利用者の方も大変なのに逆にこちらが励まされ、とても力をもらいました。今でもあの時の瞬間は、忘れることができません。 震災から2週間後デイサービスが再開された時は、誰からともなく自然と拍手が湧き起こりました。いつもと変わらない利用者の方の笑顔にまた力をもらい、皆さんとデイサービスで再会できたことを心から嬉しく思い、それと共にここまで一緒に頑張りぬいた仲間や励ましてくれた利用者の方に感謝の思いでいっぱいになりました。利用者の皆さんに、そして仲間へ心から「ありがとう」と伝えたいです。
|
||
「辛さを忘れさせてくれる楽しいひと時にありがとう」 |
|
| ■ 佐藤幸悟・昭子(浪江町) | ありがとうの言葉(46) |
震災当日は、人工透析に通っていた日で透析の機械とベッドに必死にしがみつきながら、 地震が収まるまで耐えていました。まもなく 原発事故を受けて、慌てて腎臓の薬と毛布だけを持って、近所の方の車で避難し、津島の避難所まで避難しました。そこから人工透析ができる病院のある所ということで、二本松市内まで移動し、避難所生活を経て今の仮設住宅へ入居しました。 今の病院に通うようになってから、仲良くなった人同士で誰からともなく、「お花見をしよう」、「佐藤さんの焼肉がいいな」と話が出て、病院の看護師さんやスタッフさん、同じ仮設住宅にいる透析の仲間を交えて、年2回お花見と芋煮会として焼肉パーティーを行っています。震災前は焼肉店を営んでいたので、カルビスープなどは皆さんに喜ばれます。看護師さん達は、万が一に備えて血圧計を持参してきてくれますし、薬のことも詳しいので心強いです。こんな楽しいひと時が先の見えない避難生活の辛さを一瞬ですが、忘れさせてくれます。病院の看護師さんやスタッフさん、同じ仮設住宅にいる透析仲間の方に改めて「ありがとう」と伝えたいです。
|
|
| 「笑って、笑って、少し泣いて」 | |||
| ■山田忠正・浩子(浪江町) | ありがとうの言葉(45) |
||
|
震災後から3ヶ月間、私たち家族は7回の移動を繰り返し、ようやく矢吹町のアパートに落ち着くことができました。孫がちょうど小学校に入学する時期でした。新しい環境での小学校生活を心配しましたが、お友達と毎日元気良く遊んでいます。ようやく生活は落ち着いたのですが、孫が3年生になるこの春、孫の母親がいるいわき市に私たちも転居することを決めました。 矢吹町での最初の6ヶ月間は、知り合いがまったくおらず、私たちは完全に孤立していました。しかし、あるきっかけで矢吹町の社協に自らSOSの電話をしたところ、すぐに生活支援相談員の方が駆けつけてくれました。坂路さん、長田さんでした。その時、それまで胸にためていたつらい思いを一気に吐き出させてもらったその夜は、震災後はじめてゆっくり眠ることができました。母親と離れて暮らす孫を守らなければという強いプレッシャー、孤独感につぶされそうな毎日、胸にため込んでいた私の気持ちのすべてを聞いてくれて、そしてとびきりの笑顔で励ましてくれました。 それから、二人と冗談を言い合って笑い合う毎日を過ごしてきました。笑って、笑って、そして少し泣いて。おかげで気持ちは少しずつ前に向かうようになりました。 この震災で失ったものはすべて私の中のアルバムのなかに入っています。だから後ろを向かず、今は新しく出会えた二人の笑い仲間に感謝の気持ちでいっぱいです。だから、今は矢吹町を離れるのがとてもつらいです。 だけど、坂路さん、長田さん本当にありがとう。たくさんの笑顔をありがとう。心から感謝しています。
|
||
「これからもたくさんの元気を」 |
|
| ■葛尾村「支え合いセンター」職員一同(葛尾村) | ありがとうの言葉(44) |
震災後3ヶ月くらいから、三春町内10箇所に私たちの村の仮設住宅が建設され、その内4箇所に集会所が併設されました。そこで私たちは「支え合いセンター」の職員として、毎日、避難されている住民の方々のご支援をさせていただいております。
最初の1年くらいは、全国各地から届けられた支援物資を住民の方々に配布してきました。集会所いっぱいになるほどのご支援は本当にありがたいことでした。その後、集会所でパッチワークや編み物、健康体操教室などを企画しながら、少しでも高齢の方が仮設住宅から外に出てきてもらえるように趣向を凝らしています。また、元全日本女子バレーボール選手の三屋裕子さんが、忙しいなか定期的にこの集会所を訪問していただき、お年寄りの方に寄り添いながら体操指導をしていただいています。皆さんその日を心待ちにしているようです。三屋さん、「ありがとうございます」。
朝は必ず各住宅を一戸一戸まわりながら声かけをしています。毎日の一声が住民の方の心を開き、反対に「毎日ありがとうね」とお礼を言われることも多くなりました。その言葉にこちらも「ありがとう」という気持ちでいっぱいです。 私たちも避難をしているので、気持ちにメリハリをつけながらがんばっています。支え合いセンターのメンバーがお互いに支え合い、自分たちがまず笑顔になることを大事にしています。そして仮設住宅の方々がいつでも笑顔でいられるように、これからもたくさんの元気をあげていきたいと思います。 |
|
| 「子どもたちのために今できることを」 | |||
| ■福島西子ども劇場 永山典子・松井美智江(福島市) | ありがとうの言葉(43) |
||
|
「子どもたちが豊かな夢と勇気と創造性を持つのびのびとした人間に育ってほしい・・・」そんな願いを持ちながら、現在280名ほどの子どもと親の会員が様々な活動をしているのが、私たちの子ども劇場です。福島市に誕生してから38年を迎えました。 震災と原発事故直後から、県外の子ども劇場の仲間やこれまで福島に舞台劇や音楽、人形劇などの公演に来ていただいたことのある創造団体の皆さんから、「大丈夫ですか?何かできることはないですか?」と、心配や励ましの連絡を多くいただきました。 これまで当たり前にできていた屋外活動は制限されてしまい、悩みながらの毎日でした。しかし、全国から多くの励ましをいただくことで、とにかく「今はここでできることを考えていこう」「動きは止めないでいこう」と、親同士が意見を出し合うことで不安感は薄らぎ前向きに進めていけるようになりました。 こうして、今も子ども劇場の活動ができるのは子どもや親がいるからこそで、皆さんと一緒に活動できることに本当に感謝しています。まだまだ普通の環境ではないなかでも絶えることのない子どもたちの笑顔に、私たち大人は“ありがとう”の気持ちでいっぱいです。 また、全国からの支援もさることながら、特に創造団体の方々がこの災害を風化させないよう、全国の公演活動のなかで福島の状況を伝え続けていただいていることはとてもありがたいことです。 |
||
「心も体も温まりました」 |
|
| ■緑川 亜紀子・遥斗(南相馬市) | ありがとうの言葉(42) |
私たち南相馬市の海水浴場近くに祖父母、両親、子どもの4世代で住んでいましたが、住宅は津波で流されてしまいました。避難した学校の3階から、水没した地域を見たときはとても信じられない気持ちでした。 避難先の学校の体育館の床に直接マットを引くだけで、大変寒いなかで5日間ほどを過ごしましたが、その地域の婦人会の方々が毎日炊き出しをしてくれて、温かい食べ物をいただくことができ、心も体もあたたまったことが今でも忘れられません。屋内退避指示が拡大するなかでも、炊き出しを続けていただいたことには本当に感謝しています。そして、今思い返しても温かいお風呂を貸していただいた友人にも、ありがとうの気持ちが沸き上がります。 その後、4ヶ月ほど福島市の親戚宅に避難をし、その間子どもたちも福島市内の学校にお世話になりましたが、息子も友達が毎日遊びに誘ってくれてうれしかったことを今でも話します。そして、昨年8月から南相馬市に戻り、子どもたちは仮設住宅から元の学校に元気に通っています。仲のいい友達と毎日過ごしている様子に母親としてホッとしています。 |
|
| 「子どもたちのために・・・ありがとう」 | |||
| ■野崎 美紀子(福島市:元保育園園長) | ありがとうの言葉(41) |
||
|
昨年、7月の夏祭りを目標にみんなで取り組んでいたときのこと。窓を閉め切ったホールで、それでも毎日よさこいや太鼓の練習を頑張る子どもたちの姿。真剣で体いっぱいに楽しさを表現していました。 私に突然抑えきれない怒りが湧き起こりました。これが子どもの現実。自然から遠ざけられ、蒸し風呂のような室内での生活でありながら生き生きとした表情を見せて頑張る子どものけなげさ。だけど子どもたちにこの環境を強いていいはずがない。みんなに知ってほしい。新聞に投稿し、掲載されました。 3ヶ月程経ち、保育園に小包が届きました。フェルトで作られたたくさんのままごと道具。丁寧に作られた野菜やくだもの、お菓子や台所のセット。手紙が添えられ、「投稿の記事を読み、自分にできることで子どもたちを励ましたい。作り続けて遅くなりましたが、遊んでいただけると嬉しいです。」世田谷の方からでした。 何のご縁もない方からの温かさ。子どもたちはとても喜び、今も大切に遊んでいます。本当にありがとうございました。 そして、子どもたち。子どものために頑張り続けた保育園の職員たち、お父さん、お母さんたちにも、大変だったのに一緒に笑顔で過ごしてくれたこと、心から「ありがとう」。 |
||
「郡山の皆様に感謝しています」 |
|
| ■山野辺 久(相馬市) | ありがとうの言葉(40) |
3月11日の大地震・大津波の後、私たち夫婦は、郡山に住んでいる娘が迎えに来てくれて、相馬市を離れ郡山の住人となりました。それから1年7ヶ月間、アパート暮らしをしてきました。 この間、郡山の方々のあたたかい心ざしを沢山いただきました。防寒用の衣類を届けてくださったり、旬の野菜を分けてくださったり、励ましの言葉をいただいたりして、お蔭様で、浜とは違う郡山でのひと冬を乗り越えることができました。 同じ町内にお住まいだったある方は、近くにある富岡町や川内村の仮設住宅の交流訪問を定期的に行っておられ、私のアパートにも何回か慰問に来てくださり、得意の尺八の演奏で「ふるさと」「浜千鳥」などのなつかしい歌を合唱して、楽しいひと時を作ってくださったことは忘れられません。手作りの置き物や旬の果物などを届けてくださったりして、心から感謝しています。 相馬市の私の住居は、海岸線から1km位の内陸で、松川浦沿いの所ですが、津波は床上1.5m位まで侵入しました。しかし、復興計画では居住制限の範囲ではないので、念のため土台を1m位地盛りして、その上に20坪位の住居を建てることにしました。 今年10月に転居しました。やはり長い間住みなれた相馬の空気は、なんと言っても心が安らぎます。愛犬のリュウも、あの津波のときは畳のへりにしがみついていて助かりました。 私たち老夫婦と犬一匹の新しい生活が始まりました。 周囲はまだまだ復興とはほど遠い状況ですが、元の姿に少しずつでも早く戻れるよう、力を合わせてがんばっていかねばと思っています。
郡山の沢山の方々のあたたかい援助により今の私があることを思い、心から感謝をしています。 |
|
| 「桃やりんごの花に癒されて」 | |||
| ■長谷川 花子(飯舘村) | ありがとうの言葉(39) |
||
|
私たち家族は飯舘村で酪農を営みながら四世帯一緒に生活していました。だけど、今では四世帯がバラバラに避難生活をしています。そんななかでも息子は多くの方の支えもあり酪農の仕事を続けています。 震災前の12月に九州旅行をした時のバスガイドさんが、震災直後、村の状況を心配してすぐにたくさんの水を送ってくれました。「ありがとう」の気持ちでいっぱいになりました。 飯舘村の仮設住宅はいくつかありますが、私たちは伊達市で生活しています。今年7月末に開催された「夏祭り」では、伊達市社会福祉協議会の方々が飯舘村を思い起こさせていただくような様々な企画をしていただきました。「相馬盆踊り」は本当に盛り上がりました。地元地区の「わらび園」のわらびもちを再現しようと、山形からわらびを取り寄せていただき、飯舘村のみんなでわらびもちを作り、参加者にふるまうことができました。 伊達市のここの場所は、周りに果樹園や畑が多くてその景色にとても癒されます。仮設住宅の皆さんは気持ちよく毎日散歩をしています。そして地域の方々といろいろと交流を図っているようです。皆さん万歩計をつけているので、「今日は何歩あるいたよ」というのが毎日のあいさつです。 今、仮設住宅の自治会の仕事をしていて心配なのが、高齢の方も多く、飯舘村に帰る日が延びるかもしれないという不安を皆さん抱えていることです。私が笑顔でいないと皆さんが不安になってしまう。皆さんの笑顔を見て自分も安心したい。そんな思いで毎日がんばっています。 |
||
「会津の三泣き」 |
|
| ■渡辺 敏正(楢葉町) | ありがとうの言葉(38) |
震災直後、楢葉町の住民の多くはいわき市の体育館などに避難をしました。避難所は断水で水がまったく使えなかったため、地元消防団に所属していた私を含む団員数名は、毎日ポンプ車で水を運び、バケツに移し替えては、避難所のトイレ用水などに使用してもらいました。 ほどなく子どもやお年寄りから優先的に会津美里町への避難が始まり、私も皆さんの移動を見届けてから会津美里町に移りました。 ここ会津美里町では、これまで地元の皆さんにとても良くしてもらっています。地域行事へのお誘い、取れたて野菜の差し入れ、野菜作りができる畑の提供などなど。町も土地を貸してくれ、町民農園として活用させていただいています。楢葉の方々も土に触れることで落ち着くようです。 私の子どもも小学校に通い、多くのお友達と毎日楽しく遊んでいる様子でホッとしています。親もこちらの福祉施設に運よく入所でき、家族皆が落ち着いて生活できていることに本当に感謝しています。 会津の三泣きと言いますが、会津の方のとっつきにくさで「一泣き」することはありませんでした。だけど、今、会津の皆さんの温かい心に触れ「二泣き」、そして、いつかの日か会津を離れがたくて「三泣き」するときがくるのかな。 |
|
| 「郡山の親切な方々、ありがとうございます。」 | |||
| ■ 猪狩 利夫 猪狩 律子(川内村) | ありがとうの言葉(37) |
||
|
今年の6月まで私たちは郡山市の仮設住宅に住んでいました。
耳の具合が悪くなり、紹介された近くの耳鼻科まで車椅子をおしながら歩いて行く時のことです。聞いた通りの道を歩いたつもりが、どうやら道を間違えたようだと気づいた時には、市内のどこにいるのかわからなくなり、困ってしまいました。そんな様子を見てか、近くで草刈をしていた方がその作業の手を止め、声をかけてくれ、ならば車で送ってあげると、車椅子をトランクに入れて、耳鼻科まで送ってくれました。 仮設住宅への帰り道は、耳鼻科の方にしっかりと聞いたので大丈夫と思ったのですが、やはり迷ってしまい、道を尋ねたガソリンスタンドの若い方がやはりわざわざ車で仮設住宅まで送ってくれました。 郡山の方々には本当にお世話になりました。川内村から離れ夜も落ち着いて眠ることができない日々でしたが、郡山の皆さんにとても親切にしてもらいました。 私の自宅は、福島第一原子力発電所からぎりぎり20キロ圏内にあるため、帰村後も村内の仮設住宅に住んでいますが、その時いただいた多くの親切には感謝の気持ちでいっぱいです。
(仮設住宅から眺める川内村の風景) |
||
「広野はがんばっているよ!」と伝えたい |
|
| ■鈴木 すみ(広野町) | ありがとうの言葉(36) |
地震直後、津波が来るからと町の高台にある公民館に避難しました。 次の日には「南か西へ」の避難指示で、平田村の公民館へ避難しました。平田村の方に本当に良くしてもらいました。 4月、2次避難所に移動した直後、大きな余震で建物が壊れ、別の場所に移りました。そこでも地元の方の厚意をいただき、感謝しています。 インターネットのつながりやボランティア活動を通して、県外の多くの方が心配をしてくれました。今でも地震があるたびにメールをくれます。 いろいろな人から励ましをもらっています。だから、これからは私たちががんばらないと、自分たちでも動かなければ、そんな思いをもつ有志で「がんばっ会」を作り、さっそく学校や駅などのゴミ拾いをしました。広野町のお母さん、これから広野町でお母さんになる人たちの不安を和らげる取り組みもします。 広野へ戻ってきて思うことは、やはり自分のふるさとが好きですということ。 「広野はがんばっているよ」と多くの方に伝えたいと思います。 |
|
| 「川内村の方々、三春町の方々に心から感謝しています」 | |||
| ■阿部 秀一(富岡町) | ありがとうの言葉(35) |
||
|
震災直後、避難指示の理由は伝えられず、ただ「川内村の小学校へ」のアナウンスで避難しました。 川内村の小学校で4、5日お世話になりましたが、この間、川内村の住民の方々が毎日親切に炊き出しをしてくれました。その後、川内村の方々も避難指示の対象となってしまいましたが、それまでの間、私たちの避難をあたたかく迎え入れていただいたことに、今でも本当に感謝しています。 今は三春町の仮設住宅に避難をしています。三春町の方々の愛情を様々な場面で感じます。仮設住宅近くの土地をトラクターで耕してくれて、私たちが農作業できる環境を作ってくれました。地元の花火大会にも招待していただきました。仮設住宅がある地区の自治会長さんなどは、私たちを訪問してくれて、苦情や困りごとが無いかを聞きに来てくれます。本当にありがいことだと思っています。 私たちも、周辺道路の空き缶拾いや草刈などに率先して取り組むことで、自分たちが今住んでいる地域に貢献し、地域住民の方々とも交流を図ることができたらいいなと思います。 そして、私たちがこの地域のために役立つことができ、さらにこの地域が良くなることにつながればうれしいことだと思います。 |
||
「あたたかい心に“ありがとう”を伝えたい」 |
|
| ■髙木 昌祺(楢葉町) | ありがとうの言葉(34) |
私は、「デイサービスセンターゆずのさと」の経営に携わっていました。 昨年3月11日の大震災の翌日から、原発事故の避難指示による避難指示を受け、利用者の皆さんほか、従業員とその家族約40名とともに、転々と避難を余儀なくされました。 現在、私はいわき市の仮設住宅に避難していますが、そので突然の避難者受け入れのお願いを快く引き受けてくださった同市の特別養護老人ホーム「高砂荘」さん、千葉県市原市の特別養護老人ホーム「辰巳萬緑苑」さんの皆様に、心から「ありがとう」とお礼を申し上げます。 |
|
| 「いつか味噌作りができるといいな」 | |||
| ■高屋敷 ひろ子(葛尾村) | ありがとうの言葉(33) |
||
|
3月11日は、畑仕事をしている最中に震災に見舞われました。
双葉町にいた息子家族とともに、ガソリンが無い中でしたが、次の日の夜には何とか会津若松市までたどり着くことができました。会津の親類宅で一週間ほどお世話になったあと、茨城の親類のところにしばらく身を寄せていました。それぞれに皆さん本当に良くしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 8月になり、今住む三春町の仮設住宅にようやく落ち着くことができました。 三春町の方々は大変親切です。仮設住宅の隣にある土地を地主さんが解放してくれました。荒地でしたが、自分たちで少しずつ草を刈り、土を耕し、苗をうえ、この夏はたくさんの野菜を収穫しています。畑仕事だけではなく、体を休めながら折り紙をしたりパッチワークをしたり、今の生活には不自由はありません。三春町の皆さんに本当に感謝しています。
ただ、葛尾村で過ごしていたときのように、また味噌作りをしたいなと思います。味噌作りには数年の時間がかかります。いつか葛尾村に戻ることを考えると、少しためらいがあるのも正直なところです。 |
||
「嘆くのではなく、感謝の気持ちを」 |
|
| ■大内 ちづ子(双葉町) | ありがとうの言葉(32) |
震災直後のあの時間は、思い返すのもつらいほどの出来事でした。 近所の家は倒壊。その中に取り残された方を救出。その後は、ガソリンがほとんどないなかでの川俣町、そして福島市までの避難。 数ヶ月が経ち、福島市内のアパートに独りで引っ越してきた頃は、毎日窓の外ばかりを見ているような憂鬱な日々を過ごしてきました。 時に現実を逃避したくなるようなときがたくさんありました。自分はいなくてもいいんだと思うこともありました。何もする気がない自分でしたので、それを心配する家族とぶつかってしまうことも多くありました。 それでも最近やっと外に出ようという気持ちが出てきました。 避難している地域の方々にせめてものお礼と、楊枝入れを手作りしては近くの病院などにお渡ししました。「てとて」という福島市社会福祉協議会が開催するサロンにも何回か参加しました。このサロンでは同じ双葉町の方々とお話をする機会も多く、気分も紛れ、そしてたくさんの励ましをもらっています。 また、最近では双葉町の仮設住宅である手芸教室で、編み物やクラフトを教えることになりました。こうしたことが今の生きがいになっています。 双葉町に戻れるかどうか見通しがたちませんが、今住む福島市に私なりに溶け込んで、これからを過ごして生きたいと考えています。 今は、すべてに嘆くのではなく、いろいろな方々に感謝をしたいという気持ちでいっぱいです。 サロンを開催してくれます福島市社会福祉協議会の方々には本当に「ありがとう」と言いたいです。 |
|
| 「朝日見てきっとカエル
|
|||
| ■宮代応急仮設住宅自治会役員一同(浪江町) | ありがとうの言葉(31) |
||
|
昨年8月からこの仮設住宅で生活をしています。 これまで住民みんなが元気で過ごせたのは、多くの方からのたくさんの支援があったおかげです。 避難当時は、寒い中での移動の繰り返しで大変苦労をしましたが、そんな時でも、炊き出しや物資、お風呂の提供など、知らない方々にいつも支援をしていただき、簡単な言葉では表せない人間のつながりを感じました。 最近、近くの高校の美術部の生徒が仮設住宅の壁に絵を書いてくれました。これまでとても冷たい印象だった仮設住宅の色が、ぬくもりのある華やかな印象にかわりました。「海から昇る太陽」、「浪江の花コスモス」を描いていただき、ありがとうございます。 これからも浪江町に帰るという「希望」と「目標」を持ち、夜明けを信じていきたいと思います。 |
||
| 「皆さんのバトンを引き継ぎます」 | |
| ■「ふくしま心のケアセンター 基幹センター」 松田 聡一郎(福島市) | ありがとうの言葉(30) |
ふくしま心のケアセンターは、平成24年2月に発足しました。 東日本大震災とその後の原発事故で、浜通りの他、中通りや会津を含む多くの福島県民が被災されました。 震災から1年3ヶ月が経過し、いまだに多くの方が慣れない避難生活を続けているなか、私たちは仮設住宅や借り上げ住宅を巡回して、被災者の方々の心の悩みに耳を傾けています。 発災当時、私は福島県精神保健福祉センターに勤務していました。迫り来る原発事故の恐怖と混乱のなか、手探りで始めた心のケア活動に対し、全国各地の自治体や病院、大学からたくさんの応援をいただきました。自分たちだけで乗り越えることが困難な試練も、たくさんの温かい支援があれば乗り越えられることを教えていただきました。 全国各地から心のケアの応援に来ていただいた皆さん、本当にありがとうございます。 皆さんのバトンを引き継いで、私たち心のケアセンターは福島の復興のために頑張っていきます。 |
|
| 「ありがとう“感謝”繋がるふる里」 | |||
| ■三浦 美佐子(本宮市) | ありがとうの言葉(29) |
||
|
とても素敵なかっこいい島国 日本
でも、世界の目には、日本が危ないとも思わせた放射能。 危ないとは言え、目には見えない、手に取って確認することも出来ない歯がゆい怖さ。 私たちは、ふる里の四季折々の自然の美しさ・素晴らしさを体感しており、この地を離れることは出来ません。自然と共に普通の生活がしたい。洗濯物・布団にも太陽の恵みを与えたい。とても悔しいです。子ども達は今でも線量計を身につけ、マスクを着用し通学、外での活動は今もまだ規制があります。
全国から寄せられる応援メッセージやボランティア活動・支援物資は心温まる優しさと希望を感じます。明るく元気に、そして子どもたちには夢もあります。 全国から見守り下さい。一日も早く安心して普通の生活が出来るようにと私たちは願うばかりです。 |
||
| 「花見山より“ありがとう”を伝えたい」 | |
| ■「花見山を守る会」代表高橋他メンバー一同(福島市) | ありがとうの言葉(28) |
3月11日の震災から1年余り経過しました。 『花見山を守る会』は、避難者の皆様のためにと今日まで支援活動を続けておりますが、これも今までご支援くださった皆様のおかげだと思っております。 福島復興のためにとボランティアに来てくださった方々、中には遠い県外、はたまた外国から来てくれた方もおりました。 様々な支援物資を送ってくださった方々、震災孤児のためにと寄付金を送ってくださった方々、個人様の他にも企業や団体様からも沢山のご支援を頂きました。 皆様のおかげで心折れずに今日まで支援活動を続けることができました。 ご支援してくださった皆様、本当にありがとうございました。 今後とも福島復興のため力強く活動してまいりますので、皆様方の変わらぬご指導をよろしくお願い申し上げます。 |
|
| 「子どもたちの笑顔に・・・」 | |||
| ■長谷川 幸子(南相馬市) | ありがとうの言葉(27) |
||
|
東日本大震災、原発事故。そして突然の避難。 あれから1年3ヶ月がたちました。 想像もつかなかった出来事に、私は子どもたちにちゃんと説明してあげられているかな・・・、子どもたちの心の中は・・・、放射能の影響は・・・、いつ戻れるの・・・、いろんな思いの中で毎日を過ごしています。 でも、子どもたちは元気です。 『いってきまあす!』の元気な声。守ってあげなくちゃと思っている私の方が、子どもたちの笑顔に、力をもらっている気がします。 最近では、三男と長女が太鼓の練習に参加させていただいています。毎週の練習をとても楽しみにしていて、太鼓の皆さんには本当に感謝しています。いつか舞台に立てる日がくるといいなあと夢見ています。 私たちは福島で頑張っているよ。 震災を経験したみんなが震災を忘れず、そして前を向いて歩んでいけますように。 |
||
| 「山木屋仮設よりありがとう・・・を伝えたい」 | |
| ■川俣町農村広場仮設集会所支援員一同(川俣町) | ありがとうの言葉(26) |
川俣町山木屋地区の住民が昨年6月26日に同町農村広場仮設住宅へ入居して以来、個人や各団体のたくさんの方々から炊き出しや物資の寄贈、催しの開催などの善意が寄せられており、感謝の気持ちでいっぱいです。 入居者は高齢者が多く、独居老人もいますが、いろいろな悩みをかかえながらも前向きにがんばっています。私達も微力ではありますが、住民の皆さんの力になれるよう全員でがんばっていきます。 言葉では表せない程のたくさんの感謝の気持ちでいっぱいです。ご支援いただいた皆様、本当にありがとうございました。 |
|
| 「周辺の住民の方々に“ありがとう”」 | |||
| ■佐野 ハツノ(飯舘村) | ありがとうの言葉(25) | ||
 |
松川工業団地第1仮設住宅は昨年7月末にできました。 私を含め、主に飯舘村から避難してきた方が住んでいますが、世帯がバラバラになり、今は115世帯中48世帯が独居の方です。村で農作業などを一生懸命してきたけど、それができなくなり精神的に滅入ってしまう方もいます。 ただ、周辺の住民の方々には大変お世話になっています。 散歩をしていると気さくに声をかけてくれます。野菜を持参される方もいます。地域のお祭りなどへのお誘いもあります。周辺住民の方々と交流を深めている仮設住民の方も多くいます。
仮設敷地内の頑張りだけでは無理があります。このような周辺住民の方々の優しさには本当に「ありがとう」の気持ちでいっぱいです。 |
||
| 「青山さんへ」 | |
| ■志賀 千鶴(浪江町) | ありがとうの言葉(24) |
私たち家族4人は、二本松市に避難する時、迷ってしまいました。
夕方になり、暗くなってきました。今日は車にとまるしかないと思いました。妹が、「とめてくれる家をさがしてくるから」と言いました。しばらくして、OKがでました。それが青山さんでした。とてもうれしかったです。その夜は、あたたかくねむることができました。 翌朝、青山さんが、「あなたたちが血そう変えて来たんだもの。とめるしかないわよ」と笑って話してくれました。 ありがとうございます。見ず知らずの私たちを、こころよくとめてくれた。感謝。感謝です。 |
 |
| 「感謝」 | |||
| ■佐藤 シゲ子(相馬市) | ありがとうの言葉(23) | ||
 |
震災から早や一年が過ぎ、夢のように暮らしてきました。
昨年の3月11日、あの時私は買い物に行く途中で、あの大きい揺れで身動きができなくなりました。 やっとの思いで助かったのも皆さんのおかげだと感謝しております。 昨年の5月からこの仮設住宅で暮らし始めて思ったことですが、その後毎日のようにこれから先のことを考えながら夜も眠れない日々のなか、お友達に「楽しく時間を過ごせるお茶会があるよ」と誘われ、皆さんの仲間入りをさせていただきました。帰りには「楽しかったね、また誘ってね」と笑えることができるようになりました。お茶会は、頭の体操、体の運動など、笑ったり、歌ったり、心が晴れ晴れします。 次のお茶会が待ち遠しいです。 お茶会を開いてくれる皆さんやボランティアの方々に心から感謝しています。 |
||
| 「春をまちわびながら」 | |
| ■水戸 花子(新地町) | ありがとうの言葉(22) |
3月11日の地震では、津波、原発、風評被害と、全く想像もできない悲しみ、苦しみをあじわいましたが、全国各地、世界各国からたくさんの支援をいただき、また、地域の方々からもやさしい言葉や援助をいただき、二人暮らしの年寄りの身には何とありがたいことかと思いました。
世界が一つになり、深い絆で結ばれたことに感謝いたします。
仮設住宅での暮らしも、たたみを入れていただき、あたたかいぬくもりを感じております。
小雪舞うきびしい寒さの中で、やがて訪れる福島の春を待ちわびていましたが、3月で98才を迎えることができました。自分の身体を大切にし、残された人生をまっとうしたいと思っております。
支援してくださった皆様、本当にありがとうございました。 |
 |
| 「心温まるボランティア活動を受けて」 | |||
| ■福島愛育園 職員一同(福島市) | ありがとうの言葉(21) | ||
 |
東日本大震災後、私たち児童養護施設「福島愛育園」には、多くの方々から寄付金、物資の寄贈、園内の除染活動、子どもの喜ぶ催しの開催などの善意が寄せられています。4月以降も遠方への旅行のお誘いが多くあり、職員一同、人の心の温かさや心強さを感じています。
ご支援をくださる皆様は「少しでも子どもたちの力になりたい」と余暇時間を割いてくださっています。それに対して当園長は常に「少しずつ恩返しをしていかなければならない」と話しています。職員全体にもこの意識が高まっており、子どもたちにもいずれ人を助けることのできる大人に成長してほしいと願っています。 改めて、ご支援をいただいた皆様には心からお礼を申し上げます。 ありがとうございました。 |
||
| 「沢山の優しさにありがとう」 | |
| ■石川 尚子(福島市) | ありがとうの言葉(20) |
3月11日の東日本大震災の時は家族それぞれバラバラでした。 子どもたちは保育所や学童の先生に守られ、励まされ一緒にいていただき、子どもたちは心強かったと思います。やっと迎えに行け子どもが無事でいてくれたこと、今でもはっきり覚えています。先生方も家族がいるなか、遅くまで我が子と一緒に待っていてくれたこと感謝の気持ちでいっぱいになりました。 地震後はガス、水道、電気のライフラインが止まりました。いつ普及できるか分からない、ガソリンもない状況となった。給水所までは遠く、水をもらいに行くこともできなかった。困っていた時「水ある?」と子どもの友達のお母さんから電話をいただき、家まで届けてくれた。みんな自分のことでいっぱいなのに嬉しかった。 同じ建物に住むときどき話す方が来てくれ、灯油を分けてくれた。その方は水が無く、困っていた。いただいた水を分けた。 お店にいっても物がなく必要な物が買えなかった。埼玉に住むいとこが大きなダンボールにいっぱいに食糧と日用品を送ってくれた。 京都に住む一緒に働いた方、中学の同級生からの励ましのメールも届いた。 地震の日から今日まで沢山の方に支えられ乗り越えられたように思います。大変なこと辛いこと沢山ありましたがその分人の優しさに気づくことができたように感じています。支えてくれた沢山の方の優しさに「ありがとう」の感謝の気持ちでいっぱいです。 |
 |
| 「子どもたちの笑顔を取り戻してくれた体育館に・・・ありがとう」 | |||
| ■福島保育所/齋藤 玲子(福島市) | ありがとうの言葉(19) | ||
 |
3月11日の震災以降、子どもたちは砂あそび、水あそびはもちろん、すべり台、ジャングル・ジムに触ることも外に出ることも制限されました。 太陽の光をいっぱい浴び、虫を見つけては捕まえて、裸足になって水をバケツで運んで砂場に川を作り、汗をかいて友だちと楽しくあそぶという子どもたちの本来の姿を見ることができなくなりました。
その様ななか、以前から交流がある聾学校さんのご好意で、福島県立盲学校の体育館を使用することが出来るようになりました。週に2回、3歳以上の3クラスが活動することになりました。 体育館に着くと、ワァ~と声をだしながら走り出す子どもたち、広い場所で思い切り走るだけで声をあげて笑う子どもたち。 ただ走るだけで、こんなに笑うのかぁ ただ走るだけで、こんなに楽しいのかぁ と、改めて子どもたちが体を動かすことの大切さを知ったように思いました。 走ること以外にも音楽に合わせてリズムを踊ったり、クラス対抗のリレーを行い大きな声で「ガンバレー!」と応援し合ったり・・・本当に子どもたちにとっては、楽しみの時間のひとつになりました。 この笑顔に私たち保育士も元気をもらい、この笑顔を見るためにこれからも頑張っていこうと思いました。 |
||
| 「すてきなお花をありがとうございます」 | |
| ■福島保育所/中村 洋子(福島市) | ありがとうの言葉(18) |
保育所の庭は放射能除去ということで、野菜を育てていた畑も花壇の花も木もすべてなくなってしまいました。玄関先にあった山椒の葉には毎年のようにアゲハチョウの幼虫が生まれ、子どもたちが観察するのにもってこいの葉っぱだったので残念です。 保育所の子どもたちは外へも出られず、庭には草もない状況がつづき、各家庭で咲いた花を部屋に飾ることもできない状況でした。そんな時、花屋を営んでいる保護者の方が玄関にそっと花をおいていってくださいました。それからも季節を通じでいろいろアレンジして玄関先を飾ってくださいました。花が置いてあると、玄関先から保育所が明るくなったように思いました。毎日登所する保護者の方や子どもたちも元気を頂いたことと思います。 すてきなお花をありがとうございました。 |
|
| 「ありがとう 感謝の気持ちでいっぱいです」 | |||
| ■福島保育所/永澤 孝子(福島市) | ありがとうの言葉(17) | ||
|
昨年の10月、突然福島保育所に電話がかかってきました。天然水を差し上げたいという内容のものでした。最初のうちは、個人からの支援は信じられず本当なのかなという気持ちでしたが、保育所の天然水はすでに底をついていましたので頂くことにしました。 10月27日木曜日、横浜市から5時間かけて獣医さんである小林健二郎さんと東京都の長堀恵美子さんがニコニコ顔で、6本入りの天然水を32箱も運んできて下さいました。‘福島の子どもたちを内部被爆から守りたい’という一途な気持ちで運んで下さったようです。 その後も何度も水を運ぶために福島保育所に来ていただきました。今では子どもたちが飲むお茶ばかりでなく、給食用の水として使用させていただいております。全国の方々は福島の子どもたちに対して何かしてあげたいと思っているそうです。そういう方々に呼びかけて、小林さんと長堀さんは天然水を運んでいるということでした。 福島保育所の子どもたちは徐々に元気になってきました。これからも‘健やかにたくましく’育ってほしいと願っております。 毎回、天然水を届けて下さる小林健次郎さん・長堀恵美子さん、そしてご支援いただきました全国の皆さん、ありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。 左が小林さん 右が長堀さん |
||
| 「ハワイのおじちゃんありがとう」 | |
| ■荒 芳久仁(新地町) | ありがとうの言葉(16) |
私が初めて、竹林さん親子にお会いしたのは、23年5月3日のことでした。避難生活の時、焼きそばの炊き出しに来てくださいました。うまかったです。焼きそばってこんなにうまいものとは。。。。。 あの時は着るものも食べるものも本当にすくない状態でした。しかし、竹林さんの荷物のなかにはたくさんの衣類やお菓子が詰めてありました。英語の包装なので、不思議に思いたずねると、ハワイで仕事をしていて、「ムーブフォージャパン(今自分に出来る事)!」という気持ちで被災された方に支援をしていると説明されました。 それから毎月焼きそばの炊き出しが続いております。ある時「資金は大丈夫ですか?」と聞くと日本で支援してる写真を見て、ハワイの方が募金してくださるとのこと。また、町の方にも支援金として寄付して頂き、人のつながりってスゴイものだと感じました。 竹林さんが支援してるのを知り、次から次へと自分も手伝いたいと申し出られ、外人の方が多数加わってるそうです。 2月19日で9回目の支援となりました。 子どもたちも焼きそばを頂くと「ハワイのおじちゃんありがとう」とのかわいい声。また新地町に来たいという気持ちになるとか。 竹林さんはじめ、多くの方々の支援に、私達も仮設の仲間とともに、仲良く協力しあい、助け合い、感謝し、前を目指していきたいと思います。ありがとうございました。 |
|
| 「ありがとう」 | |||
| ■阿部 洋子(相馬市) | ありがとうの言葉(15) | ||
 |
3.11東日本震災まさかの出来事、早いもので一年になりました。 私と主人を高台にある磯部小学校に早く避難するようにと言って、息子はその後に部落の消防車を出して、住民に避難するように呼びかけていたと思います。子2人とお母さんは学校にいたので助かりました。あの大きな津波で家も船もそして消防団員であった息子の命まで亡くなってしまいました。
3ヶ月間避難所にいて6月から仮設に入りました。電化製品はほとんど入っており、うれしくて涙がとまりませんでした。避難所にいた時からこれまで、一年間いろいろな形で世界中の皆さんから支援して頂きまして、本当にありがとうございました。毎週お茶会があるので参加しております。おかげ様で皆で楽しく体を動かし体操をしながら元気に笑顔で頑張っております。 支援して頂いた皆さんに感謝の気持ちを忘れる事なく、前進して参ります。 |
||
| 「絆」 | |
| ■横山 和子(相馬市) | ありがとうの言葉(14) |
被災してから、はやくも1年になります。当時はこれからどのように生活していったらいいのか本当に不安でいっぱいでした。当時、2日間は隣りの家で本当にお世話になり、涙を流し別れて来ました。心からありがとうと礼をして、3ヶ月間母親ひとりでくらしている所にころがりお世話になりました。 金銭の面まで世話になり、老いても親に世話になって百泊百礼も出来ず、仮設に移ってからは知らなかった人とも親せき以上のつきあいにまでなり、今に至っています。絆というか本当に世話になり、またお互いに出来る事は世話をし、ちょっとの被災物資も分け合って生活して来ました。 全国いっぱいの方々にもありがとうとお礼を心より申し上げます。復興し生活も落ちついて、もしまたこのような事態になったら、私事ながらお返しが出来る事を願いたいです。 本当に皆様のささえがあったからこそここまで進めたのです。心からお礼申し上げます。 ありがとう。 |
 |
| 「郵便局のポケットティッシュ」 | |||
| ■M(大熊町) | ありがとうの言葉(13) | ||
 |
大熊町に住んでいた私は、避難所や福島県内の親戚の家を転々とした後、新潟県へ移動しました。
そして数日後、更に新潟から埼玉県への避難が決まりました。
埼玉へ移動する前に、郵便局へ行きました。窓口で対応してくれた若い女性は、私の車のいわきナンバーが目に入ったのか、「もしかして…避難されて来たのですか?」と聞いてきました。私がそうなんです、これから埼玉に移動するんですと伝えると、励ましの言葉をかけてくれました。用事が終わり私が郵便局を後にしようとした時、その女性が「あ、少しお待ち下さい!」と言い残し、裏手に行ってすぐ戻ってきました。戻ってきた女性の両手には、沢山のポケットティッシュがありました。女性は「これくらいしか出来ませんが…」と、両手いっぱいのポケットティッシュを渡してくれました。着の身着のままの避難生活で何もかも1から揃える状況だった私にとって、沢山のポケットティッシュは本当にありがたかったです。 その場でお礼は言いましたが、今度新潟を訪れる機会があれば、また改めてお礼を言いたいです。本当に感謝しています。 |
||
| 「忘れない暖かいお風呂」 | |
| ■菱川 昌子(相馬市) | ありがとうの言葉(12) |
今まで経験した事もない、大震災・大津波から早一年になります。
私達家族五人は、相馬市立向陽中学校に避難しました。毎日のように余震と寒さで夜が来るのが恐ろしかった。色々考えて、すっかり落ち込んでしまい、どうしようかと思ったりもしました。
それから何日か過ぎて、「自衛隊の方たちにより今晩からお風呂のサービスがある」との放送がありました。本当にうれしかった。広島より来たのだと言って私達を暖かく迎え入れてくれ、風呂の入り口には女性の隊員が一人一人に「いらっしゃいませ」と声をかけて下さいました。あの時の事は決して忘れることができません。ありがとうございました。いつもきれいな風呂で感謝の気持ちでいっぱいです。遠い所より来てくれて、ありがとうございました。
全国からの支援物資・励ましの言葉、本当にありがとうございました。 今は一歩前に進んで仮設住宅で親子五人、肩を寄せ合って暮らしています。 全国の皆さんに心より感謝の気持ちを忘れず、ありがとうの心で…。 |
 |
| 「人間って素晴らしい」 | |||
| ■江田 節子(浪江町) | ありがとうの言葉(11) | ||
3月12日、浪江から避難が始まり、親戚の家から二本松市の体育館まで夢でも見ているような、信じられない光景でした。 しかし二本松市の方が見ず知らずの大勢の私達を受け入れ、支援してくれた事に感動しました。いままで他人事のように思っていた大災害、もし立場が変わり、支援する側になったら支援したい、とこの時強く思いました。 その後も行く先々で皆さんに声を掛けて頂き日本人いえ世界中の人間ってやっぱり素晴らしいと感じました。 いま前を向いて歩いて行けるのは、私に関わっている全ての人達のおかげです。ありがとうと全員の皆様に言えないので、これからも前に進んでいくことが、ありがとうかなと思っています。 |
|||
| 「思い」 | |
| ■河西 チイ子(相馬市) | ありがとうの言葉(10) |
昨年の恐ろしい津波、今でも夢の様だ。でも本当なのだ。 目に入れても痛くなかった孫の美沙が津波に遭い、いない。 私の家は大家族。家で息子と孫二人で漁に出て、帰ってきたら家族みんなで手伝いをした。息子も孫も一生懸命働いてくれた。孫家族は4人。全部で9人だった。 3月11日午後2時46分、私達は立っていられず、家の戸口につかまり地震のおさまるのを待った。まさかあんなに大きな津波が来るとは誰も思わなかった。私も爺さんも。 ところが、嫁がラジオで大津波の情報を聞き、機転を効かせて、毛布3枚その他いくつか持って車2台で磯部小学校に避難した。その時、となりの爺さんは誘っても逃げなかった。5~6人亡くなった。 孫は消防団に入っていたので、私達とは別行動だった。津波がゴーと音を立てて来たのは学校に避難してから30分後でした。孫を心配していたが、夜になって孫はずぶぬれで帰ってきた。その時消防団員何人かが行方不明とのことだった。 娘孫は地震後、会社より家に帰る途中で津波に遭いました。家が心配で早く帰って来たかったのだろう。磯部は一面湖になった。家も一軒もなくなった。水が引けて孫をさがし歩いた。一週間後に車の中で見つかった。どんなに寒かったと思うと3ヶ月くらい毎日涙が止まらなかった。 気持ちが一転した。食べ物も着るものもなんにも無いその時、支援物資を頂いた。こんなに有りがたく思った事はなかった。時が経って、仮設ができて入居出来る事になった。その時もボランティアの方々より色々とお世話になり、外国からもいろいろとご支援いただいた事、忘れる事が出来ません。この様な温かい有りがたい事を私に出来るかと思います。 これからどうなるのか不安でなりません。でも生前孫美沙の良く手伝ってくれた事には感謝したい。前向きに考えること、何か楽しみを見つけていくしかないと思います。 どうしても孫美沙の事は頭から離れない。学校時代のバレーの試合で、全国各地家族で応援に行った事忘れられません。私もこれから何年この世にいられるかな。 |
|
| 「紀州農園の梅干し」 | |||
| ■原田 澄子(南相馬市) | ありがとうの言葉(9) | ||
  |
避難という突然の環境の変化に主人は体調を崩し、あづま体育館での毎日菓子パンと水の食事に塩分を欲しがりました。 コンビニに行っても食料品の棚は空でしたが1パックの梅ぼしが残っているのを見つけ買ってきました。「梅ぼしがこんなにおいしいものとはじめて気づいた」という病人の言葉に製造元の紀州農園に感謝の気持ちと福島にも早く食品流通が良くなることを願っている旨のハガキを出しました。 その後農園より励ましのお手紙と梅ぼしはじめいろいろの支援物質が送られてきてびっくりしました。そして、私達避難エリアの皆さんで分けあってごちそうになりました。 「被災地の復興と気持ちをしっかりもって頑張ってください。」の遠く和歌山からのお手紙に、先の見えない空しい不安病のような日々を過していた私でしたが、しっかり肩に手をかけていただいたような力強さを感じました。 原田 澄子 様 拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、有難く厚くお礼申し上げます。 この度は、弊社商品を、ご購入頂きまして誠に有り難う御座います。 さっそくですが、震災後1ヶ月が経ちましたが、突然の地震、津波、さらには原発の被害では被災地に深い爪痕を残しました。被災された方々に心より御見舞い申し上げます。その大変さは私たちが経験したことのない想像以上だったと思うと、一人でも多くの方の無事と今避難されている方々の、安心で穏やかに過ごせる生活が一日でも早く戻ることを毎日毎日祈っています。 出来るだけ早く、被災地が復興する事を心から願います。どうか気持ちをしっかり持って頑張ってください。遠く和歌山県から祈っています。 敬具 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川2400番地 株式会社 紀州農園 取締役 業務統括本部長兼工場長 岩田 好文 |
||
| 「までいな取り組みで一致団結」 | |
| ■飯舘村社会福祉協議会職員一同(飯舘村) | ありがとうの言葉(8) |
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故につながり、さらに計画的避難区域の指定による全村が避難ということになり、私たち村民の生活を一変させるものとなりました。 社会福祉協議会では、行政と一緒に村に戻れる日まで健康でいるために、スタッフはもちろんですが、モチベーションを高めていくためにはどんなことが必要なのか日々考えながら、生活支援相談員活動、物資配布、イベント調整に笑顔で対応しています。 全国からのさまざまな支援をいただき、感謝、感謝の毎日です。ほんとうにありがとうございます。 |
 |
| 「龍の年『復興元年』は笑顔で一歩一歩昇ります」 | |||
| ■新地町社会福祉協議会 職員一同(新地町) | ありがとうの言葉(7) | ||
 |
4月21日災害ボランティアセンターの活動開始後、北は北海道から南は沖縄県まで、海外からも、ボランティア活動に協力していただき、本当にありがとうございました! 大被害を受け、あの膨大ながれき『被災財』を、多くのボランティアの皆様のパワーとご支援のおかげで、8月に早期収束できましたことに、心から「ありがとう」を申し上げます。 被災した町民は、4月から6月までに応急仮設住宅に移り、生活を始めております。町外の方の仮設住宅は8月から生活が始まりました。ボランティアセンターの名称は、8月から生活支援ボランティアセンターに移行しました。活動は、主に仮設住宅の生活支援に変わり、 炊き出し、お茶会、足湯、各種イベントなどです。8ヶ所の仮設住宅の住民は、全国から嬉しい支援を沢山いただいて、大変喜んでいます。 生活も、だいぶ慣れて来たようです、笑顔で、元気に前を向いて、少しずつ前進しています。仮設生活は長期になると思いますので、これからも細く長く 継続してご支援を賜りますようよろしくお願いします。 |
||
| 「“さくら”の笑顔が戻ってきました」 | |
| ■アクセスホームさくら(二本松市) | ありがとうの言葉(6) |
3月11日の震災後、「アクセスホームさくら」は避難を余儀なくされ全員ばらばらになってしまいました。
「もう一度、みんなで仕事がしたい!」との思いから、8月1日に二本松市で事業を再開することができました。利用者さん全員は戻ってくることはできませんが、13名の笑顔が戻ってきました。 私たちの取り組みをNHKさんが放送してくださったことがきっかけで、全国の方々から暖かいご支援、励ましを頂きました。 新たにお菓子作りをすることになり、東京都世田谷区の「わくわく祖師谷」さんからは、寄付を募った義援パンの提供から、ラスクの作り方まで支援を頂き「パンDEラスク」が完成しました。今では、たくさんの方から注文を頂くようになりました。 大阪からは、家具や木工、陶芸など物づくりの仲間の方々が来てくださり、おいしい本場のたこ焼きをみんなで焼いてたべました。とっても元気になれた1日でした。 本当にたくさんの方々の応援を頂いて、“さくら”の笑顔が戻ってきていることに心より感謝する毎日です。 |
 |
| 「これからの未来」 | |||
| ■石塚由実・中学2年(福島市に避難中) | ありがとうの言葉(5) | ||
 |
私が「ありがとう」を伝えたい人は、自衛隊の方々です。私の家は、海に近くなかったので津波には巻き込まれずにすみましたが、私の祖父母の家が津波によって全部ながされてしまいました。大好きだった祖父母を突然奪ったあの波。 祖父母の発見された写真を見ると、これは、現実なのかっと思うような町の風景でした。まるで戦争でもあったかのようでした。自衛隊の方々は、家族のために一所懸命遺体を見つけていて私はとても感動しました。 私の大好きな家族を見つけてくれて本当にありがとうございました。私は、これからの人生、祖父母に恥じぬように生きていきたいです。そして、まだ行方不明のご家族を1日でも早く見つけてあげてください。 |
||
| 「井戸水をありがとう」 | |
| ■S・H(福島市) | ありがとうの言葉(4) |
今回の地震では、直後から停電、断水となり、まずは水の確保が急務でした。福島第一原発が爆発し、やがてその事態の深刻さを知るであろう放射能が迫る中、給水所には屋外で順番を待つ人の長い行列。しばらくこうした日が続くことを覚悟しました。 しかし地震から3日後、実家の近くで農業を営む家で、井戸水を提供してくれているという情報があり、さっそく伺ってみると、入り口に「水あります」の手書きの看板が。ちょうどその家の方が外に出ておられたので、「水をいただけると聞いたのですが・・・」というと、「どうぞ、どうぞ。遠慮なく汲んでいってください。」とのお返事。見ればその方の家も塀が崩れ、蔵の壁も大きく落ちている・・・。自らの被害もよそに、水で困っている人を想いやるその方に、助け合うことの本当の意味を理解しました。結局、お言葉に甘えるかたちで、大きいポリバケツを台車に載せてその後も何往復かし、長い行列に並ぶことなく、必要な水を十分にいただきました。本当に助かりました。ありがとうございました。 |
 |
| 「希望に向かって」 | |||
| ■浪江町サポートセンター杉内 一樹デイサービスセンター /木幡孝男(浪江町) | ありがとうの言葉(3) | ||
 |
3月11日、一樹デイサービスセンターはいつも通りの時間を過ごしていました。そして地震発生。利用者さんは互いにしがみつき「早く揺れが収まってくれ」と叫ぶ人、物が倒れないように必死に支える人・・・、恐怖におののく時間でした。 津波が来て安全な場所まで移動する車中で見た町の風景は無残な姿でした。不安な一晩を過ごした翌朝は原発からの避難命令・・・、利用者さんと一緒に避難しました。そういうなか避難所として受け入れていただいた郡山市のあかね福祉様には美味しい味噌汁をご馳走になりました。猪苗代町の福島県ばんだい荘様には暖かい体育館を用意して戴き、職員の皆様にも何から何まで良くしていただきました。二本松市の安齋裕子様には自宅を提供していただき畳で寝ることができました。ほかにもたくさんお世話になりました。皆様方のご厚情は忘れません。この紙面をお借りして御礼を申し上げます。あれから9か月・・・ 私たちは福島県をはじめ関係機関の支援を受け10月3日より二本松市で避難している方々を支援する浪江町サポートセンター杉内のなかでデイサービス事業を再開することができました。サポートセンターにはこれまで全国各地より多くの支援が寄せられています。誠にありがとうございます。そのご厚意に心から感謝をするとともに、「いつの日か浪江町に帰る」を合言葉に、希望を失わず前を向いて一歩ずつ踏み出して行こうと思います。 |
||
| 「お父さんありがとう・・・」 | |
| ■H・T(伊達市) | ありがとうの言葉(2) |
3月11日の東日本大震災の日、私たち家族にとっても忘れられないことがあります。
子どもたちは学校、私は職場、そして主人は岡山から新幹線で福島へ戻っているところでした。実は、翌日には次男のサッカーの大会の応援に戻って来ていました。
主人から、「今、京都付近だから、夕方頃福島へ到着するから」とお昼に連絡がはいりました。
その後、震災になり私は慌てて自宅へ戻りました。すると子どもたちはびくびくしながら外に出ていました。 そして、心配なのが主人です。携帯も繋がらず…連絡がつかずにいました。 初めて連絡がとれたときは、夜遅くでした。 宇都宮から新幹線を降りて、歩いて近くの体育館に避難していると連絡がありました。子どもたちも心配していて、私が「お父さん無事だった」と話すと、泣いて喜んでいたのが記憶に残っています。 そして、翌朝主人はレンタカーを借りて、ちょうど福島の人たちが数人避難所にいて一緒に福島へ帰ってきました。この話を聞いてビックリ!! 無我夢中で家族のところに少しでも早く帰りたいという一心で帰ってきてくれたのです。 そのとき、家族の絆を改めて実感しました。 あの時言っていなかった言葉 「お父さんありがとう・・・」 |
 |
| 「突然のプレゼント」 | |||
| ■特定非営利活動法人 コーヒータイム/代表 橋本由利子(浪江町) | ありがとうの言葉(1) | ||
 |
私達は、3月11日の地震の後、翌12日にはメンバー15名とスタッフ5名は、それぞれ家族と伴に故郷を離れました。 その時はこの様な事になるとは夢にも思わず、2~3日地元を離れていれば良いと考えていました。避難生活が1ケ月、2ケ月と続くなか、これから先のことが、大変不安になりました。 浪江に帰る日を待った方が良いのか、それとも新しい地で、コーヒータイムを再オープンさせた方が良いのか。 たまたま、そんな私達の悩みを新聞が取り上げてくださり、みず知らずの人達から、プレゼントや義援金が届くようになりました。その中に手作のミトンが何組か送られてきました。私達は浪江町で活動している時、手作のピザが自慢でした。「あ、このミトンで、もう一度新しい場所でピザ生地を作ろう」と決心させてくれました。今は台所の片すみにぶらさがっているミトンですが、仕事の合間にながめては、あの時、決心させていただいた事を思いだしています。 又、多数の方々からご支援をいただきました。一歩一歩前に進むことを、背中をやさしく押していただいていると感じています。 |
||
【記事一覧】