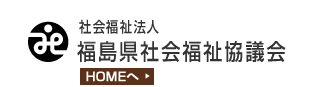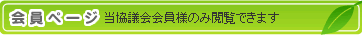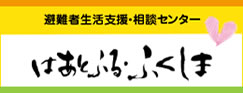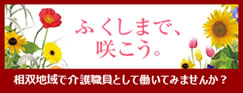福島県社会福祉協議会
お知らせ
「共済事業資産の外部委託に関する説明会」(平成21年2月5日開催)において契約者の皆様からお寄せいただきました質問内容です。ご参考ください。
【質問1】
三菱UFJの資料の中で(p4)、一定の積立比率を下回った場合、追加の掛金負担が発生することにも注意が必要とありますが、年度途中での掛金の変動が発生する場合もあるということでしょうか。また翌年度に掛金が増減する場合、何月に具体的掛金が通知されるかお尋ねします。
【回答1】
確定給付企業年金制度のような場合、給付水準は一定とし、掛金によって将来の給付に見合う積立比率を維持していきます。
本会共済制度も「財政計算」の実施により将来給付に対する適正な掛金率を検討していきます。ただし、その時期は共済事業規程第21条1項に規定のとおり、年金数理に基づいた財政計算を原則として5年に1度実施することにしていますので、基本的にはその際に掛金率の見直しを行います。
また、「財政決算」の結果で、運用成績が大幅に下ブレした場合など、積立が一定の積立比率を下回れば、財政再計算の時以外であっても掛金見直す場合があります。
これらの結果を受け掛金率を見直す場合には、規程を改正することになりますので十分に共済契約者の皆様に説明をし、同意確認が得られたのちに具体的な掛金率の変更を実施します。
【質問2】共済事業規程第6条第3項の規定について
同規定において、前項(第2項)の場合の契約解除については、加入者掛金分のみが返還され、事業主負担分については、返還されないとのことですが、第6条第1項の規定の届け出による契約解除の場合も事業主掛金分の返還はされないとお聞きしました。それについては、どこに規定をされているのでしょうか。また、事業主分は返還しないとする理由、経緯、根拠(法的根拠を含む)等をお示し願いたい。
【回答2】
第6条1項の契約解除の届け出があった場合は、共済事業規程細則第2条に基づき加入者掛金分のみを返還することになります。
例えば福祉医療機構が実施します「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」では、そもそも医療機構も共済契約者も自由に共済契約を解除することができないことになっています。したがって共済契約者が行う解除は、すべての被共済職員の同意を得た場合にだけ行うことができ、この効力は将来に向かってのみ生じることとされています。
一方、積立方式の本共済制度の場合は、積立不足が発生している場合に全額給付すれば、残っている会員の掛金負担が大きくなる可能性があることや、大量脱会があった場合に、スケールメリットを生かした資産運用が出来なくなることなどを理由に、共済契約者の利益を守る観点から、本制度の共済契約の解除にあたっては事業主分の過去の掛金分は返金していません。
【質問3】責任所在について
仮に信託銀行の破産や資産運用による損失等により、退職金制度に重大な問題が発生した場合については、共済契約者(各法人)が責任を負うこととなるのか確認をしたい。また、今までの県社会福祉協議会で自家運用している場合であっても責任所在については同様に共済契約者である各法人となっていたのか確認をしたい。
【回答3】
仮に資産運用を委託している信託銀行が破産した場合でも、信託法により信託財産は守られます。しかし、専門家による資産運用であっても運用リスクが生じることはあります。この場合、資産の積立額が増減するという点で各共済契約者の皆様に影響が及ぶ可能性はあります。このように共済契約者が最終リスクの引き受け手(掛金負担)となっている代わりに、共済制度実施団体である本会は受託者責任(善管注意義務・忠実義務・分別管理義務・情報開示義務)を負っており、財政管理については運用基本方針に基づいた専門性のある運営を行っていくことにしています。
【質問4】金融商品取引法について
今回の外部預託については、金融商品取引法に抵触するためとの説明であったが、仮に一法人で同じように、職員から資金を集め国債等の有価証券で運用した場合も法的に抵触すると考えられるがそれでよいか。
【回答4】
一般的に職員から資金を集めることは、労働基準法に定める「労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約」(強制貯金)の禁止にあたる可能性があります。また、労働契約に付随せず、労働者の委託を受けて貯蓄金の管理を行う(任意貯金)場合にも、貯蓄金管理協定を締結する必要があるなど合法的な手続きをとる必要があります。
個々具体的なケースにもなりますので、この点についてはさらに確認を必要とします。
【質問5】資産運用の職員周知について
今回説明のあった資産運用に係る職員周知ということは、黙示という意味で職員の同意は法的にも必要ないと理解してよいか。なお、法的に必要ないとした場合であっても、職員の同意については契約者である各法人の判断により対応することとしてよいか。
【回答5】
資産運用に関する「運用基本方針」内容については、加入者個々の同意を書面で確認するまでは必要としません。ただし、内容を各加入者に対して適切に説明していただくことが大切です。この点を踏まえたうえで、最終的な意向の判断については各共済契約者による対応で結構です。
【意見6】運用受託機関の評価について
運用受託機関の評価については、5年ごととしていますが、期間が長く感じました。何故、5年としたのかわかりませんが、期間を短くし(できれば毎年)評価することが必要ではないでしょうか。
【回答6】
「運用基本方針」では運用受託機関の評価を5年ごととした理由は、共済事業規程第21条1項に定める財政計算の実施に合わせたためです。運用機関の評価は中・長期的な視点で行う一方、金融機関がガイドラインを忠実に実行しているか、期待どおりの収益率と効率性を実現できているかについては、四半期ごとに報告を求めチェックをします。
四半期ごとの報告の際には本会とミーティングを行っていきたいと考えます。
【意見7】信託法第37条の加入者の周知について
県社協においては、加入者に対して、業務概要(掛金納付状況、資産運用状況、財務状況)の周知に努めるとしていますが、その周知については、四半期ごととし、受託機関からの報告書及び県社協と受託機関のミーティング結果を報告書という形で資料提供していただけないでしょうか。
【回答7】
運用業務に関する四半期ごとの報告内容につきましては、共済契約者の皆様にその都度資料提供する予定としています。なお、ミーティングを実施した際は、その結果を例えば事務説明会などを通してできる限り共済契約者の皆様に伝達していきたいと考えています。
【質問8】
全契約者の4分の3以上の同意が得られなかった場合、県社協としてはどういう方向性を示すのか。
【回答8】
同意が得られなかった理由を明らかにし、また「運用基本方針」の内容を検討して改めて契約者の皆様に提案することになります。
【質問9】
運用する場合、信託銀行への委託しか選択肢は無いのか。
【回答9】
生命保険会社の一般勘定や投資顧問会社による運用もあり得ます。しかし、「生保一般勘定」は、元本と一定の利回りが保証されているとはいえ解約控除付となっていて以前ほど商品としての魅力がないこと、投資顧問会社については、アクティブ運用でコストも高く商品選定にあたっても専門性が必要なこと、また最低受託残高も一般的に10~50億円とハードルが高いことなどから、共済事業規程第19条3項では信託業務を行う金融機関との信託契約のみ規定しています。
【質問10】
資料p16グラフ1で掛金と給付の表が平成29年までありますが、以後10年の推移は給付が掛金を逆転するのですか。
【回答10】
資料中のグラフは、今年度実施した財政検証の結果によるものですが、将来予測の前提として、期初の加入者を平成20年度からの3年間はこれまでの実績ベース(毎年270人)で増加させ、平成23年度以降は10,004人で固定させています。したがって、将来予測で平成29年度にほぼ掛金額と給付額が均衡するのは上記前提があるためですが、その都度財政決算及び財政計算を行い、適正な掛金率について検証を行い、十分な給付が行えるように制度運営をしていきたいと考えています。
【質問11】
現在までの掛金と給付との収益率は何%ですか。
【回答11】
平成19年度中の掛金額に対する給付額の割合は67.9%でした。また、平成18年度につきましては69.4%でした。
【質問12】
共済事業に係る通信運搬費等の必要経費及び規程の第4章第15条2の一般会計への繰入金支出額の原資は、利子配当金等の果実分を充てるのでしょうか。
【回答12】
共済事業に係る必要経費等は、共済契約者の皆様からの掛金収入により充当していきます。給付につきましても掛金を財源とし、この差額分をその都度運用資産に組入れ、またその資産運用による利息収入も新たに資産へと組入れていきます。
【質問13】
委託している信託財産の中から信託報酬が支払われるのでしょうか。
【回答13】
信託契約の内容にもよりますが、基本的に信託報酬は信託資産のなかから支払われます(資産から差し引かれます)。
【質問14】
退職手当給付金や慶弔金等の給付については従来どおり県社協からの送金になるのでしょうか。
【回答14】
各給付金ついては従来どおり本会から直接各契約者へ送金します。